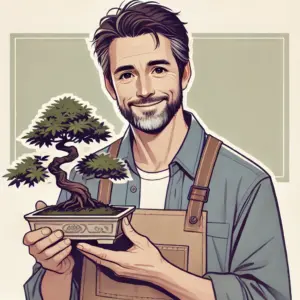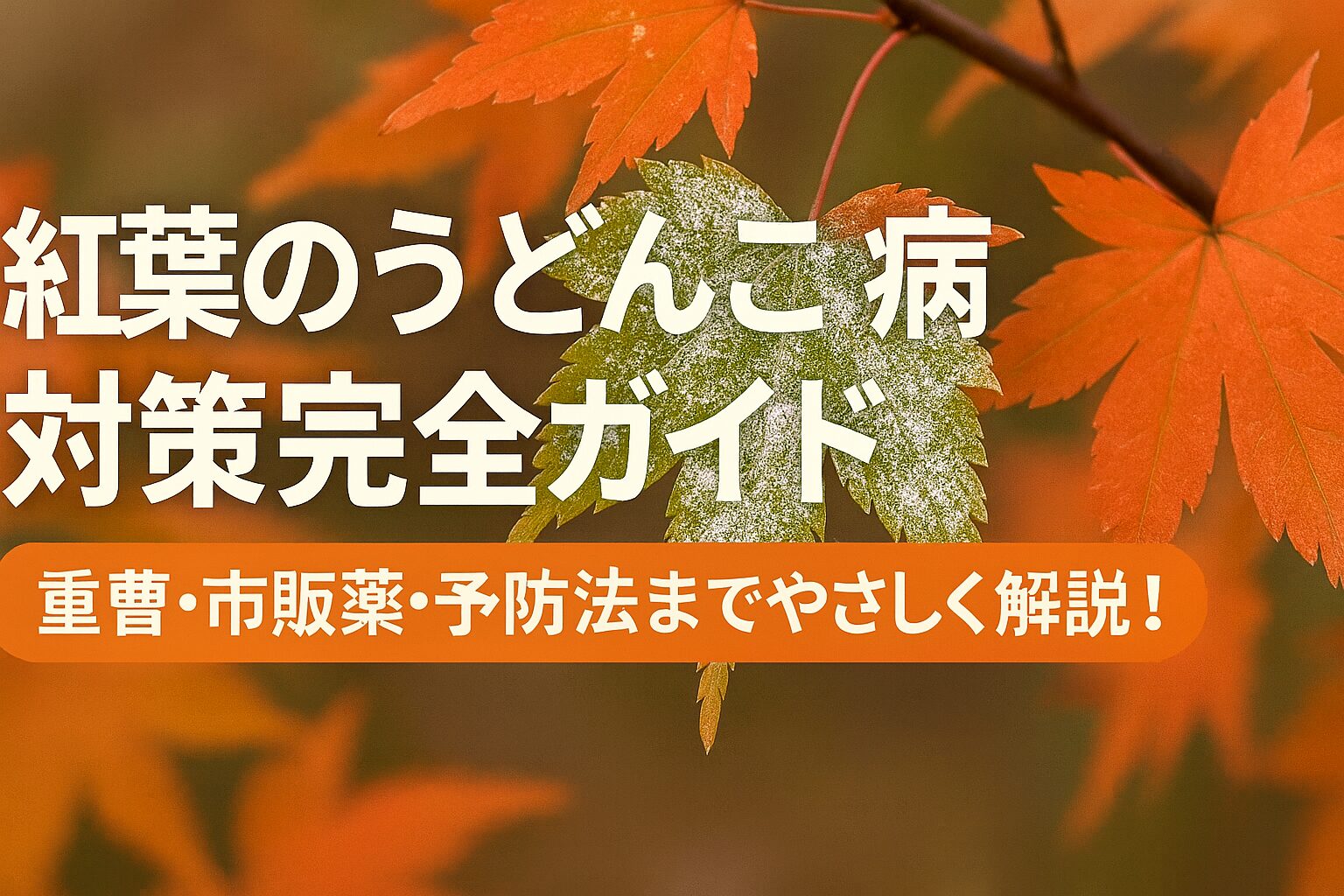美しい紅葉を楽しみにしていたのに、気づけばもみじの葉や幹に白い斑点が出ていてお困りではありませんか。
それは「うどんこ病」かもしれません。この病気の原因や、うどんこ病が何月に発生しやすいのか、気になりますよね。
もみじを襲うこの病気は、放置すると翌年にも影響が及ぶ可能性があり、早めの対策が非常に重要です。
この記事では、家庭で気軽に試せる重曹を使った対処法から、効果的な薬や農薬の選び方、使い方まで、紅葉のうどんこ病に関するあらゆる情報を網羅的に解説していきます。
この記事でわかること
- 紅葉に発生するうどんこ病の詳しい原因と症状
- うどんこ病が発生しやすい時期と翌年への影響
- 重曹や市販薬を使った具体的な対策と治療法
- うどんこ病の再発を防ぐための予防管理のコツ
紅葉がうどんこ病になる原因と症状

- うどんこ病の発生原因とメカニズム
- もみじの病気?幹や葉の白い斑点
- うどんこ病は何月に発生しやすいか
- 放置は危険!翌年への影響について
- 予防に繋がる日頃からの管理方法
うどんこ病の発生原因とメカニズム
紅葉(モミジ)にうどんこ病が発生する直接的な原因は、「糸状菌(しじょうきん)」と呼ばれるカビの一種です。具体的には、モミジの場合、主に Microsphaera penicillata という種類の菌が原因とされています。
この菌の胞子は非常に小さく、風に乗って遠くまで飛散します。そして、飛んできた胞子がモミジの葉や茎に付着すると、そこから発芽して菌糸を伸ばし、植物の栄養を吸収しながら増殖していくのです。
うどんこ病菌の発生や蔓延を助長する環境条件がいくつかあります。
【うどんこ病が好む環境】
- 高湿度と乾燥の繰り返し: 胞子の発芽には高い湿度が必要ですが、菌が繁殖して白い粉(胞子)を飛ばすのは乾燥した環境です。雨が降った後に晴れて乾燥する、といった天候が続くと特に発生しやすくなります。
- 風通しの悪さ: 葉が密集していると湿度が高く保たれ、菌が繁殖しやすくなります。
- 日照不足: 日光が十分に当たらない場所では、植物自体の抵抗力が弱まり、病気にかかりやすくなります。
- 肥料のバランス: 特に窒素成分の多い肥料を与えすぎると、葉が軟弱に育ち、菌の侵入を許しやすくなります。 [/ボックス]
このように、うどんこ病は単に菌が付着するだけでなく、菌が活動しやすい環境が揃うことで爆発的に広がってしまう病気なのです。
もみじの病気?幹や葉の白い斑点

うどんこ病の最も分かりやすい症状は、その名の通り、葉や茎、幹にうどん粉をまぶしたような白い斑点ができることです。
この白い粉の正体は、うどんこ病菌の「菌糸(きんし)」と、そこから新たに作られた「胞子(ほうし)」の集合体です。
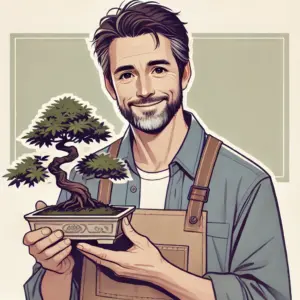
病気の進行段階ごとの症状は以下のようになります。
- 初期症状: 葉の表面に、直径数ミリ程度の白い円形の斑点がポツポツと現れます。
- 中期症状: 個々の斑点が繋がり、葉の大部分が白い粉で覆われます。葉の裏側や葉柄(ようへい)、若い枝にも症状が広がることがあります。
- 末期症状: 葉全体が真っ白になると、植物は光合成を十分に行えなくなり、生育不良に陥ります。結果として、葉が黄色く変色したり、縮れて奇形になったりし、最終的には枯れ落ちてしまいます。
一度うどんこ病にかかって変形・枯死してしまった部分は、治療しても元には戻りません。そのため、症状を早期に発見し、被害が広がる前に対処することが何よりも重要です。
うどんこ病は何月に発生しやすいか
うどんこ病は一年中発生する可能性がありますが、特に活動が活発になる時期があります。
結論から言うと、うどんこ病が最も発生しやすいのは「春(4月~6月)」と「秋(9月~11月)」です。
その理由は、うどんこ病菌が最も活発に繁殖する気温と湿度の条件が、この時期に揃いやすいためです。一般的に、菌は気温が15℃~25℃くらいで、適度な湿度がある環境を好みます。
【季節ごとの発生傾向】
- 春: 新芽が伸び、葉が柔らかい時期であるため、菌が侵入しやすく特に注意が必要です。昼夜の寒暖差も発生を助長します。
- 夏: 30℃を超えるような真夏日や、梅雨で雨が降り続く期間は、菌の活動が一時的に鈍る傾向があります。ただし、菌が死滅するわけではありません。
- 秋: 夏を越えて植物の体力が落ちてくる頃に、再び気温が適温になるため、再発しやすくなります。
- 冬: 気温が低いため発生は見られませんが、菌は休眠状態で越冬します。
特に、雨が少なく晴れの日が続く「空気が乾燥しているが、時々雨が降って湿度も上がる」という秋の気候は、うどんこ病にとって絶好のコンディションとなります。美しい紅葉のシーズンと発生時期が重なるため、こまめな観察が欠かせません。
放置は危険!翌年への影響について

「秋になれば葉が落ちるから、うどんこ病もそのままで大丈夫だろう」と考えてしまうのは非常に危険です。うどんこ病を放置すると、翌年の春に再び発生する可能性が極めて高くなります。
なぜなら、うどんこ病菌は非常に生命力が強く、巧みに冬を越す術を持っているからです。
菌は、病気にかかった葉が地面に落ちると、その落ち葉の中で休眠状態に入り越冬します。また、枝や幹に付着したまま、あるいは土壌の表面で冬を越すこともあります。
注意
越冬した菌は、春になって気温が上昇し始めると活動を再開します。そして、新しく出てきた柔らかい葉に感染し、再び病気を広げていくのです。これを「第一次伝染源」と呼びます。
前年にうどんこ病が発生した株は、土壌や株自体に多くの菌が潜んでいる状態です。そのため、何の対策もせずにいると、前年よりも早い時期から、より広範囲に病気が発生してしまうリスクがあります。
大切なモミジを翌年もうどんこ病から守るためには、秋のうちに適切な処置を施し、越冬させないための対策を徹底することが不可欠です。
予防に繋がる日頃からの管理方法

うどんこ病の対策において最も効果的なのは、病気が発生する前に「予防」を徹底することです。菌が繁殖しにくい環境を日頃から作っておくことで、発生リスクを大幅に下げることができます。
ここでは、今日から実践できる基本的な管理方法のポイントを3つ紹介します。
風通しと日当たりの確保
うどんこ病菌は、湿気が多く淀んだ空気を好みます。そのため、株全体の風通しと日当たりを良くすることが予防の第一歩です。
- 適切な剪定: 混み合った枝や内側に向かって伸びる不要な枝(内向枝)を切り、風が通り抜ける空間を作りましょう。
- 置き場所の工夫: 鉢植えの場合は、壁際から少し離したり、鉢と鉢の間隔を十分に空けたりするだけでも効果があります。
- 日当たりの良い場所へ: 可能であれば、午前中の日光がよく当たる場所で管理すると、植物が健康に育ち、病気への抵抗力も高まります。
適切な水やりと泥はね防止
水やりは植物の生育に欠かせませんが、方法を誤るとうどんこ病の原因になることがあります。
- 株元への水やり: 水やりは葉の上からかけるのではなく、土の表面に直接、静かに注ぐようにしましょう。葉が常に濡れている状態は、病気の発生原因となります。
- 泥はねを防ぐ: 土の中に潜む菌が、水やりの際の泥はねによって葉に付着することがあります。これを防ぐために、株元を敷きわらやバークチップなどで覆う「マルチング」も非常に有効な対策です。
肥料の与えすぎに注意(特に窒素)
植物を元気にしようと肥料をたくさん与えた結果、かえって病気を招いてしまうケースがあります。
特に、葉や茎を成長させる働きのある「窒素(チッソ)」成分を過剰に与えると、植物の組織が軟弱になり、菌が侵入しやすくなります。肥料を与える際は、製品に記載されている規定量を守り、成長期以外は控えめにするのが基本です。カリウムは根を強くする働きがあるため、窒素・リン酸・カリウムがバランス良く配合された肥料を選ぶと良いでしょう。
そもそも病気に負けない丈夫な株を育てるには、苗木や種子の段階からの正しいケアが基本となります。詳しい育て方は「モミジの種まき時期はいつ?種から育てる方法を解説」で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
紅葉のうどんこ病への治療と対策

- すぐにできるうどんこ病の初期対策
- 家庭で試せる重曹を使った治療法
- 症状に適した薬の選び方と使い方
- 広がった場合に使う農薬のポイント
- 治療後の再発を防ぐための注意点
- まとめ:大切な紅葉のうどんこ病対策
すぐにできるうどんこ病の初期対策
うどんこ病は、発見してすぐの初期段階であれば、比較的簡単な方法で拡大を防ぐことができます。白い斑点をいくつか見つけたら、すぐに行動に移しましょう。
症状が出た葉を切り取る
最も確実で基本的な対策は、病気が発生している葉や枝をハサミで切り取ってしまうことです。
菌が他の健全な葉に広がる前に、感染源そのものを取り除くという考え方です。切り取った葉は、胞子を飛散させないように静かに袋に入れ、燃えるゴミとして処分してください。庭や鉢の近くに放置するのは絶対にやめましょう。
注意
作業に使ったハサミには菌が付着している可能性があります。そのまま他の植物の手入れに使うと病気をうつしてしまう恐れがあるため、使用後はアルコールで消毒するか、ライターの火で軽くあぶるなどして殺菌しておくと安心です。
水で洗い流す
うどんこ病菌は、実は水に弱いという性質を持っています。そのため、ごく初期の症状であれば、ホースなどで勢いよく水をかけて菌を物理的に洗い流すのも一つの手です。
ただし、この方法はいくつかの注意点があります。
- 晴れた日の午前中に行う: 葉が濡れたままだと他の病気の原因になるため、日中にしっかり乾かせるタイミングで行いましょう。
- 根本的な解決にはならない: あくまで一時的な対策であり、環境が改善されなければ再発する可能性があります。
- 周辺への飛散: 洗い流した水が他の株にかかると、病気を広げてしまうリスクもあります。
これらの方法で様子を見ても症状が改善しない、または次々と新しい葉に発生するようであれば、より積極的な治療法に切り替える必要があります。
家庭で試せる重曹を使った治療法

「農薬はなるべく使いたくない」という場合、家庭にある「重曹(炭酸水素ナトリウム)」を使ったスプレーが初期のうどんこ病治療に効果を発揮することがあります。
これは、アルカリ性である重曹が、カビの一種であるうどんこ病菌の生育を阻害する性質を利用したものです。食品としても使われる重曹は、人や環境への安全性が高いのが大きなメリットです。
重曹スプレーの作り方と使い方
【用意するもの】
- 重曹(食用のもの)
- 水
- スプレーボトル
【作り方】
- 水で重曹を 500倍~1000倍 の濃度に希釈します。
- 目安: 水1リットルに対して重曹1g~2g程度です。
- スプレーボトルに入れ、重曹が完全に溶けるまでよく振って混ぜ合わせます。
【使い方】
- 病気が発生している葉の表と裏に、液が滴るくらいたっぷりと散布します。
- 散布は、日中の高温時を避け、曇りの日や、晴れた日の朝夕に行うのがおすすめです。
- 1週間に1回程度を目安に、症状が改善されるまで数回繰り返します。
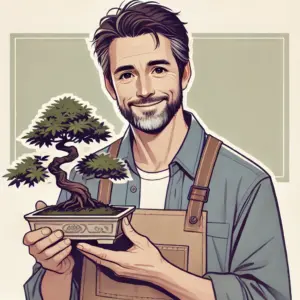
重曹スプレーの注意点
手軽な重曹スプレーですが、使用にあたってはいくつか注意が必要です。
- 濃度を守る: 濃度が濃すぎると、葉にシミができたり、生育を阻害したりする「薬害」が出る可能性があります。必ず薄い濃度から試してください。
- 効果は限定的: あくまで初期症状に対する抑制効果が期待できるもので、病気が進行してしまった場合には効果が見られないことがあります。
- 展着剤を混ぜると効果アップ: 重曹スプレーは葉の上で弾かれやすいため、食器用洗剤を1、2滴加えるなど、展着剤(てんちゃくざい)の代わりになるものを混ぜると、液が葉に留まりやすくなり効果が高まります。
重曹スプレーで効果が見られない場合は、無理に続けず、市販の薬剤に切り替えることを検討しましょう。
症状に適した薬の選び方と使い方
重曹などの民間療法で改善が見られない場合や、症状が広範囲に広がってしまった場合は、市販の園芸用殺菌剤(薬)を使用するのが最も効果的です。
園芸店やホームセンターでは様々な種類の薬が販売されており、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。薬を選ぶ際は、以下のポイントを確認しましょう。
薬のタイプで選ぶ
園芸用の殺菌剤は、主に2つのタイプに分けられます。
- スプレータイプ(そのまま使えるタイプ): 購入してすぐに使える手軽さが魅力です。うどんこ病の発生範囲が狭い場合や、初心者の方におすすめです。代表的な製品には「ベニカXネクストスプレー」などがあります。
- 希釈タイプ(水で薄めて使うタイプ): 原液を水で薄めて噴霧器などで散布します。コストパフォーマンスが高く、広い範囲に散布する場合や、定期的に使用する場合に向いています。
適用植物と対象病害を確認する
薬を購入する際は、必ず製品のラベルを確認し、「適用植物」に「かえで」や「もみじ」が含まれているか、そして「対象病害虫」に「うどんこ病」と記載があるかを確認してください。
適用外の植物に使用すると、効果がなかったり、薬害が出たりする危険性があります。
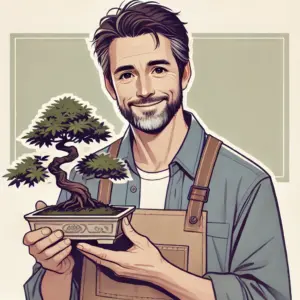
散布する際は、マスクや手袋を着用し、風のない天気の良い日の午前中に行うのが基本です。葉の表だけでなく、菌が潜んでいる葉の裏側にも忘れずに、薬液がしたたるくらいたっぷりとかけるのが効果を高めるコツです。
広がった場合に使う農薬のポイント

うどんこ病が株全体に広がってしまった場合、より効果の高い「農薬」の使用が有効な選択肢となります。農薬は正しく使えば非常に頼りになりますが、使い方を誤ると植物や環境に影響を与える可能性もあるため、ポイントをしっかり押さえておく必要があります。
代表的な農薬と特徴
モミジのうどんこ病に適用があり、一般的に入手しやすい農薬には以下のようなものがあります。
| 農薬名(商品名例) | タイプ | 特徴 |
|---|---|---|
| カリグリーン | 希釈タイプ | 炭酸水素カリウムが主成分で、有機栽培(オーガニック)でも使用可能。予防と治療の両方の効果があるとされる。食品添加物にも使われる成分で安全性が高い。 |
| ダコニール1000 | 希釈タイプ | 幅広い病気に効果がある総合殺菌剤。予防効果が高く、病気が発生する前に散布すると効果的。 |
| サプロール乳剤 | 希釈タイプ | 治療効果に優れ、すでに発生してしまったうどんこ病に効果を発揮する。浸透性があり、菌の侵入を防ぐ。 |
| ベニカXネクストスプレー | スプレータイプ | 殺菌成分と殺虫成分の両方が含まれており、うどんこ病だけでなくアブラムシなどの害虫も同時に防除できる手軽さが魅力。 |
注意
農薬を使用する際は、必ず製品ラベルに記載されている適用作物、使用時期、使用回数、希釈倍率などの使用基準を厳守してください。 これらの情報は、農薬取締法に基づいて定められており、安全かつ効果的に使用するための重要なルールです。(参照:農林水産省 農薬コーナー)
耐性菌とローテーション散布
同じ系統の農薬を繰り返し使用していると、その薬が効かない「耐性菌(たいせいきん)」が出現することがあります。
これを防ぐために、作用性の異なる複数の薬剤を順番に使用する「ローテーション散布」が推奨されています。例えば、「今回はカリグリーンを使ったから、次はサプロール乳剤を使う」といった具合です。異なる系統の薬を交互に使うことで、耐性菌の発生リスクを抑え、長期的に安定した効果を得ることができます。
治療後の再発を防ぐための注意点

薬剤散布などによってうどんこ病の症状が一旦治まっても、それで安心はできません。治療後のケアと再発防止策を徹底することが、翌年以降も美しい紅葉を楽しむための鍵となります。
土壌と株元のケア
うどんこ病菌は、治療後も土壌の表面や株元に潜んでいる可能性があります。
- 落ち葉の徹底清掃: 病気の原因となった落ち葉は、菌の温床です。株元や鉢の周りの落ち葉はこまめに清掃し、圃場の外で処分しましょう。
- 土壌表面への薬剤散布: 薬剤によっては、土壌表面に散布することで土に潜む菌を殺菌する効果が期待できるものもあります。使用する薬剤の説明書を確認してみましょう。
- マルチングの更新: 古いマルチング材は菌が付着している可能性があるため、新しいものに交換するのも効果的です。
特に、土壌環境を根本からリセットし、来シーズンの再発リスクを減らすためには、定期的な植え替えが非常に有効です。詳しい手順や最適な時期については、「モミジ盆栽の植え替え方法|最適な時期や失敗しないコツを解説」で詳しく解説していますので、あわせてご覧下さい。
翌春の予防的薬剤散布
うどんこ病が一度発生した株は、翌年も発生するリスクが高いと考え、予防的な対策を講じることが重要です。
春になり新芽が出始める前の時期や、出始めた直後に、予防効果の高い殺菌剤(ダコニールなど)を散布しておくことで、越冬した菌が活動を始めるのを抑え、その年の発生を大幅に減らすことができます。
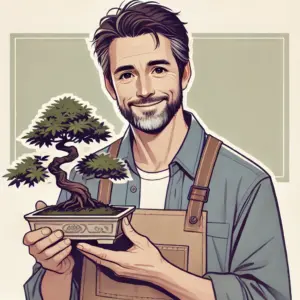
もちろん、これまで述べてきた「風通しを良くする」「適切な水やりと施肥」といった基本的な管理を継続することが、再発防止の最も基本となるのは言うまでもありません。
紅葉のうどんこ病に関するQ&A
-
うどんこ病になったモミジの葉を触ったり、もし家庭菜園の野菜に発生した場合、食べたりしても人体に影響はありませんか?
-
はい、うどんこ病菌は植物にのみ寄生するカビであり、人体には無害です。 したがって、病気の葉に触れても健康上の問題はありません。
もし家庭菜園のキュウリやナスなどに発生した場合、その野菜を食べることは可能ですが、菌によって栄養が奪われているため、風味や食感が著しく落ちています。また、見た目も良くないため、食用にはおすすめできません。
-
うどんこ病は、何もしなくても自然に治りますか?
-
残念ながら、うどんこ病が自然に治癒することはほとんど期待できません。 むしろ、放置すると風に乗って胞子が飛散し、症状は他の葉や株全体に広がっていきます。
さらに、菌は越冬して翌年の再発原因にもなるため、初期症状を見つけたらすぐに葉を取り除く、薬剤を散布するなど、積極的な対処を行うことが非常に重要です。
-
説明書通りに薬剤を散布しても、うどんこ病がなかなか治りません。なぜでしょうか?
-
薬剤が効かない場合、主に2つの原因が考えられます。
- 薬剤耐性菌の発生: 同じ系統の薬剤を繰り返し使用していると、その薬が効かない「耐性菌」が発生することがあります。この場合は、作用性の異なる別の系統の薬剤に切り替えてみてください。複数の薬剤を順番に使う「ローテーション散布」が効果的です。
- 散布ムラの可能性: うどんこ病菌は葉の裏側にも潜んでいます。薬剤を散布する際は、葉の表面だけでなく、葉の裏や茎にも薬液がまんべんなくかかるように意識してみてください。
それでも改善しない場合は、薬剤の適用病害が正しいか再度確認するか、お近くの園芸店や専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:大切な紅葉のうどんこ病対策
【症状と原因】
- 紅葉のうどんこ病はカビの一種である糸状菌が原因
- 白い粉をまぶしたような斑点が葉や茎に現れるのが特徴
- 放置すると光合成を妨げ、生育不良や枯死に至る
- 特に発生しやすい時期は春と秋の気温が15~25℃の頃
【予防のポイント】
- 予防の基本は風通しと日当たりの良い環境を作ること
- 水やりは株元に行い泥はねを防ぐのがポイント
- 窒素過多の肥料は葉を軟弱にするため避ける
【治療と対策】
- 初期症状は感染した葉を切り取って処分する
- 家庭でできる対策として500~1000倍の重曹スプレーが有効
- 症状が広がったら市販の園芸用殺菌剤を使用する
【薬剤使用の注意点】
- 農薬は適用植物に「もみじ」や「かえで」があるか確認する
- 同じ薬の連続使用は耐性菌を生むためローテーション散布が重要
【再発防止策】
- 菌は落ち葉や土壌で越冬し翌年も再発するリスクがある
- 治療後も落ち葉の清掃を徹底し菌の温床をなくす
- 翌春の新芽が出る時期に予防的な薬剤散布を行うと効果的